野口名誉教授が自国を「技術後進国」と警告
1940 年の体制維持が、日本における長期停滞の原因であったことを強調
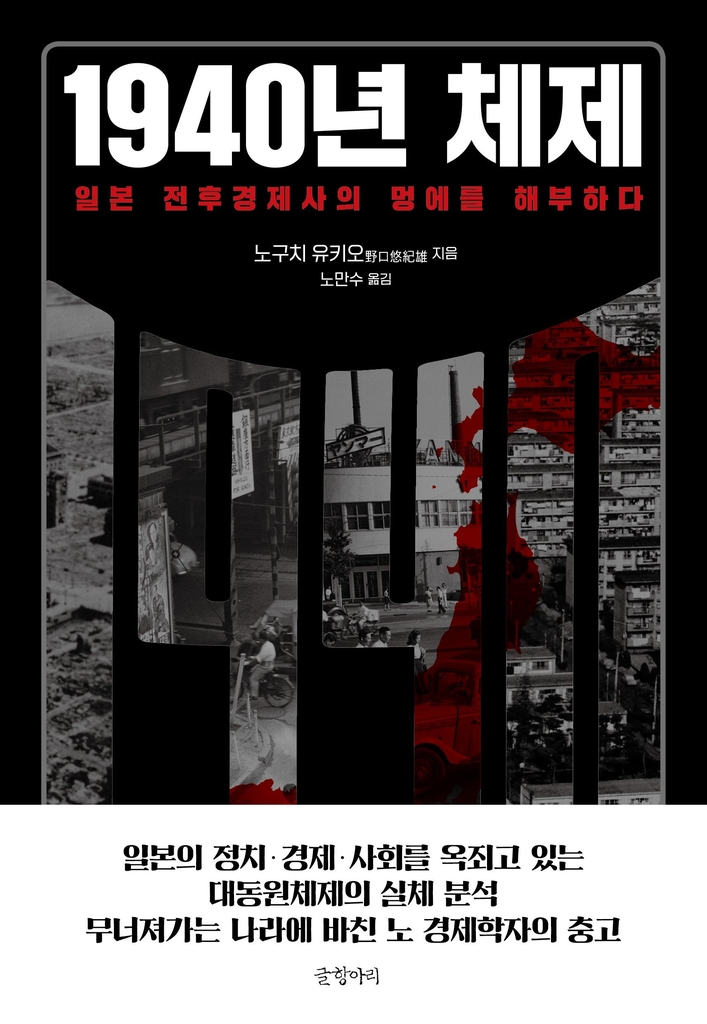
「にっぽんならでわの…」(日本でしかできない…)
近年、自国の技術や制度を詳しく取り上げるNHKなどの番組でジャーナリストがよく耳にする言葉だ。
日本の購買力平価(PPP)平均賃金が韓国に追いついた列島経済の脆弱性が最近明らかになったことを考えると、警告の代わりに「日本は素晴らしい」という警告メッセージが繰り返された.
新刊『1940年体制』(著書)は、「技術後進国」などやや強い表現で日本の体制を批判し注目を集める一橋大学名誉教授の野口幸男氏(82)が日本の経済界に送ったものだ。 ‘ この本は、警告メッセージの集まりです。
本書は、2015年に刊行された『戦後経済史』を翻訳し、2019年に同書の文庫版を刊行した後に追加したレビューです。
現地での発売時期を考慮し、韓国版は延期。
しかし、早い時期から日本の経済危機を憂慮した学者がいたことは注目に値する。

野口名誉教授がこの本を出版したのは、安倍晋三元首相(1954年~2022年)の求心力が強かった時期であり、日本の憲法史上最長の任期を記録した。
当時、黒田東彦日銀総裁率いる二次元緩和に疑問を呈する声は主流ではなかった。
経済官僚時代から異端者と呼ばれた筆者は、自分の信念を曲げず、政府や当局の認識を批判している。
この本は、デフレが 1995 年以降の日本の長期的衰退の原因であるという一般的な見解を否定し、日本が 1940 年代に確立された総力戦を繰り広げたシステムの継続が長引く停滞の原因であると指摘している。
戦後、日本は戦争のために構築した体制を変革し、商財務省(大蔵省の前身)などの経済官僚の強い影響下で体制を維持し、垂直的な経済成長を遂げました。 大企業を中心とした一貫生産。 というのが著者の分析です。
しかし、野口名誉教授の判断は、戦後70周年(2015年)の時点で「日本の産業構造と経済システムは、当時の新しい状況に適応していなかった」というものでした。
このような観点から、筆者は安倍政権の経済政策を「戦後体制の打破」と、まさに1940年体制の復活として痛烈に批判している。
この政府介入制度は 1980 年代以降その効果を失っているが、日本は依然としてそれを主張していると指摘されている。
1940年体制下で日本経済が直面している構造的危機を説明するために、彼が4歳のときに経験した東京大空襲の思い出、1964年に大省で公務に就いた後の逸話、そしてその衝撃を書いています。アメリカ留学を経て帰国して感じたこと。 個人的な経験が有効に活用されました。

著者が分析した日本人の意識の進化も興味深い。
アメリカに留学していた1960年代後半、日本は極東の小さな島国であり、日本人は「世界から学ばなければならない謙虚な考え方」を持っていた.成長。
この姿勢は日本の発展にプラスの役割を果たしたが、1980年代になると「我々は世界の上流階級だ」という考えが広まり、日本人は傲慢に陥った。
野口名誉教授がスタンフォード大学で教えていた2003年当時、中国人学生は400人以上、韓国人学生は300人以上だったが、日本人学生は100人にも満たなかった。 状況。
筆者は、日本の地価上昇に関連して初めて「バブル」という言葉を使うなど、来るべき危機を告げるために「誰にもわからない孤独な戦い」を率いたことを回顧している。
しかし、野口名誉教授は1992年に出版された著書『バブル経済』で「バブルは崩壊したが、日本の製造業は依然として強い」と書いたとき、それは完全な判断ミスだったと告白している。
「歴史のどこにいるのかを知ることは非常に難しい」という古い学者の言葉は、長く記憶される本です。
能満寿訳。 372ページ。
/ユンハプニュース

「インターネット狂信者。邪悪な主催者。テレビ狂信者。探検家。流行に敏感なソーシャルメディア中毒者。認定食品専門家。」





![[카드뉴스] 日本の電気機器技術を超えた韓国電気機器規格(KEC)を国際標準へ!](https://m-bagle.jp/wp-content/uploads/https://www.hellot.net/data/photos/image/thumbnail_1574324707.PNG)

